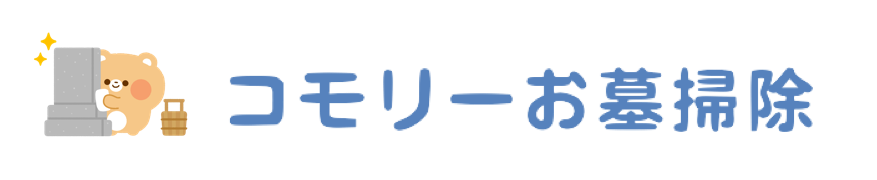お盆やお彼岸にお墓参りにいくという方も多いと思いますが、いったいいつお墓詣りに行くのがいいのか、本当のところはわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、理由も含め、お墓詣りに適した時期についてお伝えします。お墓詣りにいついけばいいのか理解したい、マナーを守ってお墓詣りをしたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
お墓参りに適した時期とは?お彼岸やお盆?
お墓参りに最も適した時期は、お盆や春秋のお彼岸、月命日や祥月命日などとされています。それぞれの時期には深い意味があり、適切に選ぶことで先祖との絆を強めることができます。それぞれの時期について、お墓参りに適している理由も含め、解説します。
お盆
お盆は、先祖の霊が家族の元に帰ってくるとされる大切な時期で、新暦の8月13日(盆の入り)から16日(盆の明け)を一般的にお盆と言います。
この時期にお墓参りを行うことで、先祖の霊を供養し、家族との絆を深めることができると考えられています。また、家族や親戚が集まりやすい時期でもあるため、皆で一緒にお墓参りをする良い機会です。お盆は、心を込めて先祖を偲ぶ時期として、多くの家庭で大切にされています。
春のお彼岸
春のお彼岸は、自然の移り変わりを感じる時期で、先祖に感謝の気持ちを伝えるための特別な機会です。春分の日を中日として、前後3日間の時期をさし、昼と夜の長さがほぼ等しくなる春分の日を含むため、バランスの取れた時期とされ、先祖供養にふさわしいと考えられています。春のお彼岸にお墓参りをすることで、日常から離れ、静かな時間を過ごすことができます。
秋のお彼岸
秋のお彼岸は、秋分の日を中日とした前後3日間で、先祖を偲ぶためのもう一つの大切な時期です。秋分の日を中心としたこの期間は、季節の変わり目として、自然と向き合いながら先祖に感謝するのに適した時間です。秋のお彼岸は、春のお彼岸と並んで、多くの人々が墓参りを行う時期であり、家族と一緒に過ごす時間を大切にする良い機会でもあります。
月命日
月命日は、故人が亡くなった日を毎月供養するための日です。この日にお墓参りをすることで、日々の生活の中でも故人を思い、供養の気持ちを忘れずに保つことができます。月命日は、個々の家族ごとに違うため、他の日と重ならない静かな時期にお墓参りができるという利点もあります。故人を身近に感じたい時に、月命日は最適です。
祥月命日
祥月命日は、故人が亡くなった年の同じ月日にあたる日です。この日は特別な意味を持ち、家族や親戚が集まり、改めて故人を偲ぶ大切な日とされています。お墓参りを行うことで、故人とのつながりを深め、日常の感謝の気持ちを再確認することができます。祥月命日は、一年に一度の特別な機会として、多くの家庭で大切にされています。
お墓参りに行かない方がいい日は?
お墓参りに行った方がいい日があるのと同様に、お墓参りに行かない方がいいという日もあります。仏滅や友引き、29日といった日は避けた方がいいといわれているので、覚えておきましょう。

まとめ
今回は、お墓参りにいつ行った方がいいのかについて紹介しました。厳格にこの時期でなくてはという決まりがあるわけではないですが、それぞれの時期や習慣を理解しておくと、お墓詣りに際に役立つと思いますから、ぜひ覚えておいてくださればと思います。